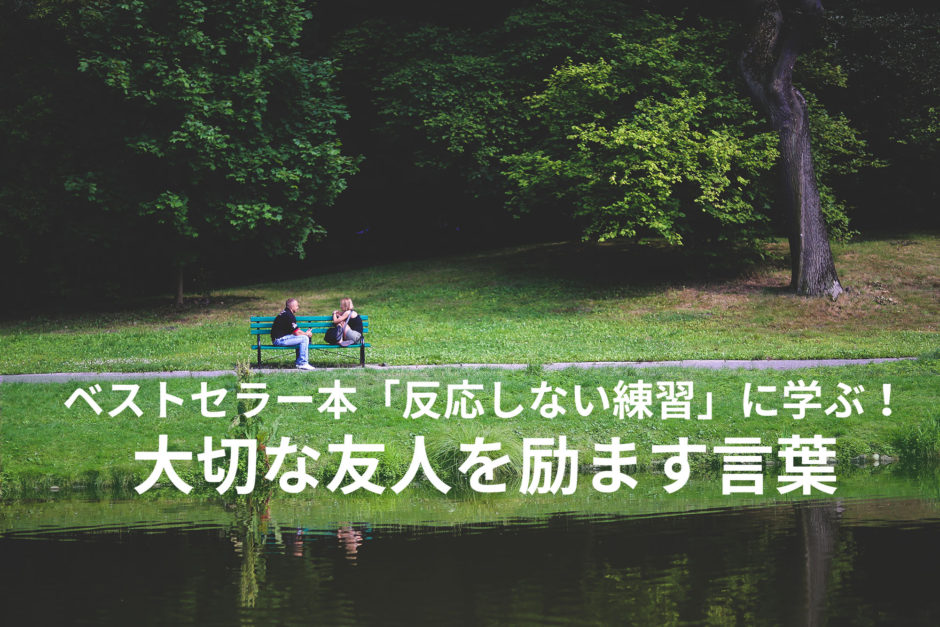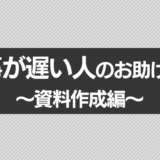「職場に高圧的な人がいて、毎日しんどい。」
「仕事でよく怒られる。先日も大きなミスをしてしまった。向いていないのかな。」
「他人の目が気になって常に気疲れする。」
「ラインの返事が返ってこない。嫌われることしちゃったかな…。」
毎日生きていると必ずといっていいほど誰かしらと関わりますよね。
金八先生が言うように人は人によって支えられることも事実ですが、人によって悩まされることもまた事実。
そんな人間関係の悩みを合理的に解決できる本があるという評判を聞き、さっそく読んでみました。その本が「反応しない練習」というお坊さんが書かれた本です。
この本には、✨ブッダ✨の教えをもとにした「悩まない考え方のコツ」が書かれています。宗教チックさは一切なく、人間関係の悩みを解決する実践的なヒントが多くて読みやすかったです。

読みながらふと頭に浮かんだのが、1人の友人でした。彼女は、転職後の職場で人間関係に悩んでおり、メンタルがボロボロになっていました。
この「反応しない練習」の内容は、彼女を励ませるように感じたのと、同じように悩んでいる方にも伝えたいと思い、今回記事としてまとめることにしました。
直接的な手助けは何もできませんが、少しでも気持ちを軽くしてもらえる言葉が1つでもあると嬉しいです。
もくじ
1.悩みをなくそうと気負わないで
「悩みをなくすこと」がゴールになっていませんか?
驚くかもしれませんが、悩みはなくそうとしなくていいそうです。「反応しない練習」によると、大切なのは悩みを理解すること。悩みの理由を正しく理解できると「悩み」は「解決できる課題」に変わります。
悩みの正体とは、何でしょう?
それは、手放せない怒りや後悔などの「執着」です。悩みを手放せない原因は、心の反応のせいなのです。反応に対する結果がうまくいかないから悩むそうです。
悩まないためには、無駄な反応をしない心がけが有効なのです。(それができたら苦労しないわ!と怒られそうですが、対処方法についてはこれから記述します。)
2.判断に気がつくと気が楽になるよ
この本によると、悩みの原因の1つに「判断しすぎる心」があるようです。(思い返すと私も日々何かしらの判断をしているなぁ…。)
まずは、「いい・悪い」「好き・嫌い」という判断をやめることがよさそうです。「こうでなければ」という思い込みが、「完璧主義」や「頑張りすぎてしまう」性格をつくり出してしまうそうです。またそれが「自分はだめだ」という自己否定にもつながってしまいます。
あなたも私も「完璧主義」の傾向があるよね。似たものどおし、通じ合う部分が多いものね。「完璧主義」って時にはプラスに働くけど、私たちの苦しみの原因はこの「判断」にあるように思いました。
では、どうやったら判断を手放せるのか?
「判断は頭の中にしか存在しない妄想」これに気づくことが重要だそうです。まずは「あ、判断した」と気づく練習を一緒にしてみよっか。
3.誰しもが失敗を経験する だから自分を責めないで
失敗したと思うことは、人生全般に必ず誰しもが経験します。
大事なのは、そこで凹まず自分を否定しないことです。あなたは責任感が強いから「評価を下げたかも」「自分は向いていない」など、自分を責めてしまいがちなところがあるかもしれません。
でも、人は判断しないという訓練を積んでいません。だから「否定してはいけない」「ありのままを受容することが大事」と頭では理解できていても「でも自分は・・・」と判断してしまうものなんです。
そんな時は、散歩をしたり、外の世界を意識することがおすすめだそうです。その際に、「思考」ではなく「感覚」を意識することが重要です。
空の色や空気の匂い、足裏の感覚を観察してみましょう。そのときに存在するのは「感覚」です。一時的かもしれませんが、苦しい「思考」から、解放されるはずです。何度でも付き合うよ。

4. 自信なんてなくていいんだよ
「もっと自信があれば人生うまくいくのに」と思っていませんか?
私もこの本を読むまでは思っていました。✨ブッタ✨によると、自信がある・ないというのも判断にすぎないそうです。
仏教では「自信という判断」は後回し。それよりも先にやらないといけないことがある。やるべきことをやって、自信がある人以上の成果をあげる という思考をするそうです。

「自信」とは「自分はこれができる」という「判断」なのでしょうか?
仮に一度は成功しても、状況は常に新しく変わるので、次もうまくできるとは限りませんよね。過去の成功をもとに自信がついたといっても、その自信は次の状況には通用しないのです。
そう考えると、自信なんて考えなくてよさそうですね。先のことはわかりません。それより「今できることはなんだろう?」と考えてみよっか。
5. 失敗してもいいからとにかくやってみよう
「自信がないからしばらく様子を見よう」「自信をつけたいから頑張ろう」と無理したことはありませんか?
しかしいくら無理しても頑張っても、自信がもてる状況はたぶん来ないようです(泣)
というのは、思考の始まりが「自分はまだまだ」というネガティブな妄想だからだそうです。その思い込みを手放さないと「自分はできる」という思いを持つことはできず、いつまでも自信がほしいという思いに駆られてしまいます。
唯一自信をもてることがあるとすれば、「こう動けば。成果がでる」という見通しが立つようになったとき。
それは、行動・体験の積み重ねのあとに初めて持つことができるものです。
だから、まずはただやってみるだけでいいようです。今この瞬間に何の判断も必要ないんですね。私は下記の言葉にハッとさせられました。
何をすればわからなければ、何をすればいいですか?と聞くだけです。
やり方がわからなければ、どうしたらいいですか?と聞くだけです。
教えてもらったら、ありがとうと言うだけです。
迷惑をかけたら、ごめんなさいと素直に謝るだけです。
そして「頑張ります」と最初の思いにたちます。
反応しない練習 93ページ
やってみて、少しずつできるようになって、経験を積んで、ふと振り返ったときに「ああ、これだけ続けてきたんだ」と思える場所にたっていること。すると、ある程度成果が出せるという見通しが立つようになる。そのときに感じる手応えが「本物の自信」です。
反応しない練習 94ページ
6.手強い相手と関わる時の立ち向かい方
生きていれば、手強く、厄介な相手にも遭遇しますよね。あなたは立ち向かっている真っ只中かと思います。
どう向き合えばいいのか?そのヒントも本に載っていました。
つい反応してしまう状況でこそ、あえて大きく息を吸ってはいて覚悟を決めて相手をただ理解するよう努めましょう。心の半分は相手への理解に、心のもう半分で自分の内側の反応をみることに使いましょう。
こちら側が相手と同じ反応を返せば、相手との反応の応酬になってしまいます。この時の問題は相手に負けることではなく、反応することで「自分の心を失う」ことです。
反応しない練習 103-109ページ 参照
相手はいつでも初めて会った人と考えること。
私たちは自分も相手も昨日と同じ人物だと思っています。ですが実はその人は見た目や名前は同じかもしれませんが、本当は別人なのです。だって心は変わっているから。
自分自身だってコロコロと変わり続けています。相手だって同じです。人は互いにコロコロ変わり続けているので、いつも新しく向き合っているのです。
反応しない練習 115-117ページ 参照
7. ときには逃げることも大事!
人と関わるときに大切なのは、反応しないことだと学びました。でもこれは、相手に無関心でいるとか、我慢することではないようです。
ただ我慢するというのは、正確には相手に我慢しているのではなく、自分の怒りを抑え込んでいる状態なんだそうです。すでに怒りは湧いてしまっているので、そのまま我慢し続けると、どんどん苦しくなります。
あなたは今、理不尽な相手に無理して我慢していませんか?こういう時は、自分の心の状態を意識的にみてあげてくださいね。

必要な場合は、反応の源を断つことも時には効果的なようです。なかなか踏み切れない場合は「いずれは、理解しあえるかもしれない」と思いながら、距離を置いてみるのはいかがでしょうか。
人の心は無常で状況も変わるので、とりあえず距離をおこうと考えるのです。
8.心の護身術として反応しない練習をしてみない?
他人に振り回されず、悩まない人生をおくるために大切なことは「心をみること」「理解すること」と、この本で学びました。
加えて、慈悲喜捨という4つの心がけを意識することも重要だそうです。
慈:相手の幸せを願う心
悲:相手の苦しみ・悲しみをそのまま理解すること
喜:相手の喜び・楽しさをそのまま理解すること
捨:手放す心、反応しない心、中立心ともいいます
人々の苦しみをまずは思いやること。「みんな、よく頑張っているな」と思うことです。もしそう思えるなら、世界は少し違って見えるかもしれません。
反応しない練習 172-177ページ
普段からこの心構えをもつことができたら、気持ちよく生きることができそうですね。
私たちには、生きてきた年数分だけ凝り固まった思考のクセがついています。すぐに、こんな✨ブッタ✨の達観した考え方に切り替えることは難しいかもしれません(悲)

ですが、私たちの人生は私たちのものであって、他人に侵食されるものではありません。
心の護身術として、頭に入れておくのはどうでしょうか?
私はあなたの才能やこれまで努力してきた過程を知っています。だからこそ周囲に振り回されず、持っている素晴らしい才能を最大限に発揮してほしいです。

出典:「反応しない練習」 草薙龍瞬 著(KADOKAWA)
友人を励ますつもりで、この記事を作成しましたが、私自身にとっても励みになる内容になりました。ありがとうございます!