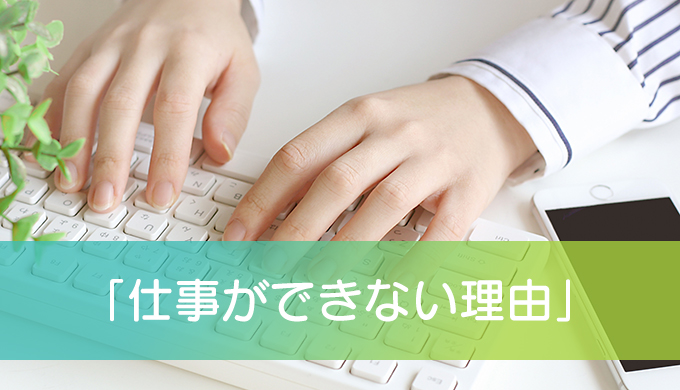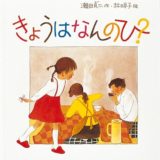このブログを読んでいる方の多くは勤め人だと思いますが、みなさんは毎日の仕事を楽しめているでしょうか?
辛いことも多いけれど、なんだかんだで仕事は楽しい……
そう思えていたら最高ですよね。
私は社会人になって7年目。
何度か転職もして、色々と経験も積みました。
それなりに大きな企業にも勤めました。
ですが、正直に言って、今でも全然
「私、自分に自信あります!」
とは言えません。
仕事が嫌いかと言われたら、そうではない。
むしろ大半の時間を仕事に割いている。
頑張っているはずなのに、なかなか仕事で自己肯定感が持てない……
私が特殊というわけでもなく、こんな風に感じている方は多いようです。
自分の時間の大半を費やす仕事が辛いと、
日々の幸福度はなかなか上がりません。
いきなり変わるのは無理でも、
明日からの人生がちょっとだけ楽しくなるように。
私達が仕事ができない理由、一緒に考えてみましょう。
もくじ

私達は、どうして自分が「できない」と感じるのでしょうか。
成果を全く出していない?
真面目に働いていない?
おそらく、そうではないはずです。
本当に真面目に働いておらず、なんの成果も出していない方は、そもそもこんな記事を読まないでしょう。自分ができることをちゃんとやって、真面目に働いていれば、全く成果0なんてことはまずあり得ません。
会社の要求レベルが高く、現在の実力が足りていなかったとしても、採用したのは会社です。ベストを尽くしているならば、自己否定に向かう必要はないはず。
頭では分かっていても否定的になってしまう時、そこには常に「他人」の影があります。
私の例で言えば、たとえばこんな時、簡単に落ち込んでしまうのです。
・上司の要求に応えられず、がっかりさせてしまったと感じた時
・同僚と比べて、自分の仕事の成果が些末だと感じた時
些細なことで落ち込む人は大抵の場合、大なり小なり他人を意識しすぎています。自分の中に明確な価値基準がないから、自分を他人のものさしで測っているんです。
そんな人にとって「仕事ができない」と周囲に思われる人こそ「仕事ができない人」。
他人は、他人の思惑で動きます。自分でコントロールできません。
だから、いつまでたっても周囲のさじ加減で、「仕事ができない人」になってしまう。
これって、辛いことですよね。
さて、他人に影響されて落ち込んでしまう人が、そんな状況を変えるには
①周囲に認めてもらう
②周囲からの評価を気にするのをやめる
のどちらかしかありません。
わたしはずっと①を目指して四苦八苦していたのですが、
最近はどちらかというと②を意識しています。
話が変わりますが、少し前に、以前大ブレイクした書籍「嫌われる勇気」を読みました。
最高に気になるタイトルだなあと思いつつ、ずっと読めていなかった本です。
「嫌われる勇気」は、「哲人」と「青年」という登場人物の対話を通してアドラー心理学の考え方を紐解いていくという内容なのですが、その中に特に印象的な考え方がありました。
「課題の分離」です。
課題の分離は、自分の課題と、他者の課題を分けろ、という考え方です。
「嫌われる勇気」の続編、「幸せになる勇気」にこの考え方を分かりやすくまとめた箇所があるので、抜粋します。
人生のあらゆる物事について「これは誰の課題なのか?」という観点から、「自分の課題」と「他者の課題」を切り分けて考える。たとえばわたしが、上司に嫌われているとする。当然、気持ちよくはありません。なんとか好かれよう、認めてもらおうと、努力するのが普通です。しかしアドラーは、それは間違っていると断ずる。わたしの言動、またわたしという人間について、他者(上司)がどのような評価を下すのか。これはその上司の課題(他者の課題)であって、わたしにコントロールできるものではない。わたしがどれだけ好かれる努力をしても、上司はわたしを嫌ったままかもしれない。
岸見一郎、 古賀史健(2016)「幸せになる勇気」ダイヤモンド社
そこでアドラーは言うわけです。「あなたは他者の期待を満たすために生きているのではない」。そして「他者もまた、あなたの期待を満たすために生きているのではない」と。他者の視線に怯えず、他者からの評価を気にせず、他者からの承認も求めない。ただ自らの信じる最良の道を選ぶ。さらには他者の課題に介入してはいけないし、自分の課題に他者を介入させてもいけないと。
岸見一郎、 古賀史健(2016)「幸せになる勇気」ダイヤモンド社
ストレスの原因の大半は人間関係だといいますが、「課題の分離」という考え方は人間関係の根本的な部分に切り込んできます。
例えば会社であなたが上司から嫌われて、評価されないとしても、「上司があなたをどう思うか」はあなたがどうにかできるものではない。
あなたは自分のするべきこと、すなわち「自分の課題」だけを見据えるべきなのだ、と言っているわけです。

これは余談ですが、書いていて改めて、アドラー心理学のすごいところは承認欲求を真っ向から否定するところだな、と思います。
いやいや、人間って承認欲求があるから頑張れるんじゃ?なんて疑問も湧きますが、そこは同書で「青年」が声高に主張してくれますので置いておくとして。
私のように、ある意味承認欲求が強いというか、他者の目線が気になって生き辛い人間にとって、この考え方は衝撃的です。
アドラー心理学を真の意味で実践することが必ずしも正しいとは限りませんが、
「あなたは他者の期待を満たすために生きているのではない」。
そして「他者もまた、あなたの期待を満たすために生きているのではない」。
これは言われてみればその通りです。
仕事をする時、私達は会社、上司、同僚……全方位からの期待に晒されていますが、最終的には、自分が幸せであるために働くべきなんです。
辛くても仕事をがんばるのは、自分のキャリアや、やりがいのためであるべきです。目線がそちらを向いていれば、必要以上に落ち込むことはないでしょう。
逆に自分が何かアクションする時、私達はつい相手に対して「こうしてほしい」「こうしてくれるだろう」と期待しがちです。
でも、まわりの人たちだって自分が幸せになるために行動しているわけなので、時には噛み合わないのも当然なのかもしれません。
……と、こういった新しい考え方を本当の意味で身につけるには、
「生きてきた時間の半分が必要」と、同書にはありました。
私、これが身につく頃にはアラフォー終盤だなあ……
少しずつ、前進していくしかないですね。
それにしても、この本が大ブレイクするということは、日本にはこうやって窮屈な思いをしている方が本当に多いんでしょうね。
さて、ここまで「仕事ができない!」と自分を責めがちな方は大抵が気にしすぎ、という方向で話をしてきましたが、最後に本当に仕事ができていない時のことも考えてみましょう。
実際、働いていて自分で自分にがっかりするような時って、ありますよね。
人間なので、どんな仕事をしていてもミスや分からないことはでてくるものですが、あまりにも頻繁な場合はその仕事が得意じゃないのかもしれません。
その仕事が好きかどうかと、得意かどうかはあまり関係ない気がします。
好きでやっていようとも、思うようにいかないことばかりではストレスが溜まります。
私は得意な仕事と興味のある仕事が一致していないタイプなのですが、
自己評価がなかなか上がらない原因のひとつはそれでしょう。
あまりにも仕事と自分の相性が悪ければ、得意な方向に向けてやり方を変えてみたり、仕事そのものを変えてしまうのもひとつの選択肢です。
とはいえ、そもそも得意な仕事ってどうやって探したらいいんだろうなぁ……と、思いますよね。私の好きな経営者である任天堂の元社長、岩田聡さんが、人の持つ「才能」についてこんなふうにおっしゃった記録があります。
才能というのは、「ご褒美を見つけられる能力」のことなんじゃないだろうかと。「なしとげること」よりも、「なしとげたことに対して快感を感じられること」が才能なんじゃないかと思うんですよね。
ほぼ日刊イトイ新聞(2019)「岩田さん: 岩田聡はこんなことを話していた。」ほぼ日ブックス
いってみれば、ご褒美を見つけられる、「ご褒美発見回路」のようなものが開いている人。
自分が注ぎ込んだものよりも、ご褒美のほうを大きく感じる瞬間が来れば、よい循環がはじまるし、それが続くんです。
ほぼ日刊イトイ新聞(2019)「岩田さん: 岩田聡はこんなことを話していた。」ほぼ日ブックス
たぶん、人が自分の人生のなかで、「ここが得意かも」って思ってることって絶対ご褒美回路が開いてますよ。
「ご褒美回路」、素敵な考え方だなあと思っています。
たしかに好きか嫌いかとはまたべつに、かけた労力が膨大でも、
やり遂げた時の快感で全部忘れてしまう時ってありますよね。

昔、イベントで流す映像を本番3日前くらいに急遽イチから制作したことがありました。
やっている時は折に触れて挫けそうにになりましたが、
当日、動画が流れた瞬間のお客さんの歓声を聞いたらなんだか色々どうでも良くなって、「やってよかった〜!」という気分になったこと、よく覚えています。
そういう経験がある仕事は、ちょっと大変そうだなあと思ってもつい手を出してしまったりします。他の人があまりやりたがらないようなことでも。
それもきっと「ご褒美回路」が開いている、得意なことなんですね。
たとえ今は辛くても、やっていくうちに回路が開いていくことだってあるのでしょう。
そうやって、自分が気持ち良いと感じられることを増やしていったらそのうち、自分の好きなところが増えて
「私、自信ありますよ!」
と言える日がくるのかもしれません。
できれば、ご褒美回路をできるだけたくさん開いて、その回路が使える環境で仕事がしたいですね。
さて、「仕事ができない理由」の話、いかがでしたでしょうか。
今回は精神の話でしたが、「もっと仕事が早ければ……」なんて悩んでいた時に
工夫した色々なども、また書いてみたいとおもいます。
似たような悩みを持つ方々の気分が、ほんのちょっとでも上向きになっていたら、とても嬉しいです。